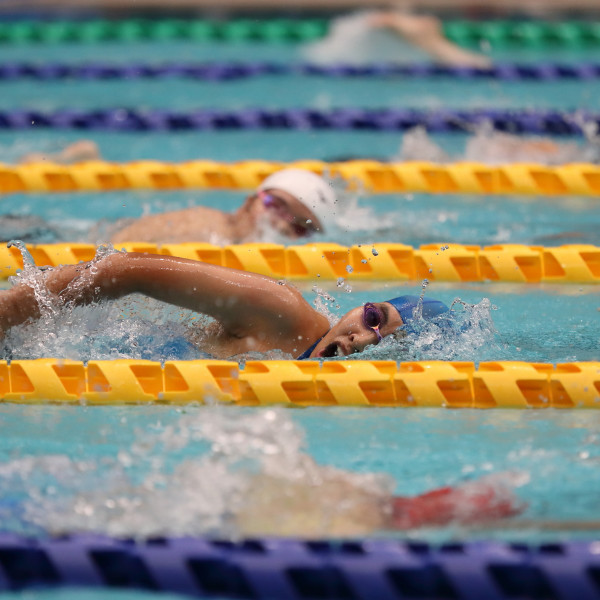JPC女性スポーツ委員会「女性リーダーに関する調査報告会」
2月19日、日本パラスポーツ協会において、JPC(日本パラリンピック委員会)女性スポーツ委員会「女性リーダーに関する調査報告会」が開催された。JPC女性スポーツ委員会では、女性アスリート、リーダーが活躍する環境整備を目指し、JPC加盟パラリンピック実施競技31団体を対象に女性役員、指導者、スタッフ等の現状把握と課題抽出を目的として「女性リーダーに関する実態調査」を実施(有効回答率100%)
調査結果報告の後、「日本のパラ団体における女性活用の可能性」というテーマで、パネルディスカッションが行われた。パネリストは、上出杏里氏(JPC女性スポーツ委員会委員/国立成育医療研究センター)、安達阿記子氏(リーフラス株式会社、元ゴールボール女子日本代表)、小淵和也氏(笹川スポーツ財団)

「海外では、女性パラアスリートが、結婚、妊娠、出産、育児というようなライフイベントを経て、競技に復帰し、トップレベルでプレーしているケースは多いが、日本では少ない。ライフイベントを経ても活躍できる環境づくりが大切だと思う。また、セカンドキャリアの選択肢を増やしていくことが次世代のアスリートの道につながっていくと思う」(安達阿記子氏)

「女性アスリート(スポーツ)委員会の委員構成男女比は、女性が91.7%で、男性は8.3%とかなり少ない。障がい者スポーツを障がい者だけで考えるのではなく、障がいのあるなしに関わらず一緒に考えていくべきものという視点と同じで、女性スポーツの問題も女性だけで考えるのではなく、男性ももっと委員となるべき。男性も自分事化して考えていくべき。障がい者スポーツは多様性が求められている、競技団体としても性別という多様性を求めていくべき」(小淵和也氏)
上出杏里氏は、「女性パラアスリートをサポートしていくためには、女性のチームドクターを増やすことが課題、加えて婦人科専門のドクターを増やすことが大きな課題だと思う」と話した。

最後に、報告会の締めとして河合純一JPC委員長から挨拶があった。「女性パラアスリートは、女性であること、障がいがあること、アスリートであること、この3つが掛け合わされた様々な障壁がある。女性パラアスリートが活躍していける環境を整えることが、我々JPCが目指していくべき方向性だ」と述べ、関係者に対して、意識を変えながら、今までの概念にとらわれることなく、より進歩的発展的な関係性を作りながら取組んでいくことを呼びかけた。
【取材・文・撮影:佐山 篤】